みなさんこんにちは!
管理人のナリアです。
今回は、昔から耳にすることがあった「バカチョンカメラ」という言葉について、改めて気になったことがあり調べてみました。
今はあまり使われなくなったこの言葉ですが、
- どんな意味や由来があるのか?
- 方言なのか?
- 蛭子 能収(えびす よしかず)さんの発言と何か関係があるのか?
いろいろ気になるところですよね。
この記事では、以下のことについてまとめていきます。
- バカチョンカメラの本当の由来
- 方言が関係しているのか?
- 蛭子能収さんが語った発言の真相
- SNS上での反応や今の扱い
昔は当たり前のように使われていた言葉でも、その意味や背景を知らないまま、なんとなく使っていたという方も多いはずです。
この機会に、一緒に確認していきましょう!

私自身も今回、調べながら「なるほど…」と納得することがいくつもありました。
最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
バカチョンカメラの由来は?意味と歴史を解説
まず結論からお伝えすると、
「バカチョンカメラ」とは、誰でも簡単に使えるカメラを指す言葉で、元は差別的な意味合いはなかったと考えられています。
この言葉が広まった背景には、日本でカメラが一般家庭に普及し始めた時代の流れがあります。
当時は操作が難しいカメラが主流でしたが、オートフォーカス機能などが搭載された簡単なカメラが登場し、「バカでも、チョン(軽く押すだけ)でも使える」といった意味合いで使われたのが始まりとされています。
また、「チョン」という言葉には昔から
「少しだけ」「軽く」
という意味の方言・俗語的な使われ方があったとも言われています。
もともとは単純に「操作がシンプルなカメラ」という良い意味で使われていたものの、時代が進むにつれて「チョン」という言葉が特定の民族を指す差別的表現として認識されるようになり、放送禁止用語として扱われるケースも増えていきました。
【📸】「写ルンです」で撮った写真、スマホで受け取れるんです! アプリ提供開始https://t.co/mPftII7KeR
一部店舗を除く全国のセブンイレブンとファミリーマートに写ルンですを持ち込んでフィルムの現像を注文すると、画像データをアプリで受け取ることができる。料金は税込み2420円。 pic.twitter.com/t5phXXvGpU
— ライブドアニュース (@livedoornews) May 28, 2025
- バカチョンカメラは「誰でも簡単に使えるカメラ」を意味する言葉だった
- もともとは差別的な意味ではなく、操作の簡単さを表現していた
- 「チョン」には方言や俗語として「軽く」などの意味がある

私も昔は深く考えずに耳にしていましたが、改めて調べてみると「そうだったんだ!」と驚くことばかりでした。
次は、その「方言」説についてももう少し詳しく見ていきますね!
バカチョンカメラは方言なのか?その真相を調査
「バカチョンカメラ」という言葉には、「方言が由来では?」という説もあります。
結論からお伝えすると、
「チョン」という言葉自体は、日本各地で昔から使われていた俗語・方言として存在していたということがわかっています。
具体的には、
- 「少しだけ」「ちょっと」
- 「軽く叩く」「印をつける」
といった意味合いで、「チョン」という表現が使われていた地域が複数確認されています。
たとえば、江戸時代の商人言葉や古い大工道具の説明書きなどにも、「チョンと押す」「チョンと印をつける」といった表現が残っており、この言葉自体は特定の民族や地域を指すものではなかったと考えられます。
そのため、「バカチョンカメラ」も元々は単なる方言的なニュアンスが含まれていたという説が有力です。
- 「チョン」という言葉は昔から日本各地で使われていた
- 意味は「軽く」「少しだけ」といったニュアンス
- 特定の民族や差別的な意味ではなかったと考えられる

今回調べてみて、「チョン」自体はもともと身近な言葉だったんだなと改めて感じました。
次は、蛭子能収の発言との関係についても詳しく見ていきましょう!
蛭子能収の発言との関係は?エピソードと背景
バカチョンカメラという言葉が広く知られるようになった背景には、蛭子能収さんの発言が関係しています。
まず押さえておきたいのは、蛭子能収さんがテレビ番組内で「バカチョンカメラ」という言葉を使った場面です。
過去にNHKの番組へ出演した際、蛭子能収さんは次のように発言しました。
- 「昔はバカチョンカメラって言ってましたよね」
- アナウンサーから「今は使わない方が…」と注意を受ける
- そこで「バカでも韓国人でも撮れるカメラって意味で…」と冗談めかして言い直す
このやり取りが放送されたことで、視聴者の間で「蛭子能収さん=バカチョンカメラ発言」という印象が広がりました。
ただし、この発言はあくまで冗談交じりのもの。
蛭子能収さん本人に差別的な意図があったわけではないと考えられます。
もともと「バカチョンカメラ」は、
「誰でも簡単に使えるカメラ」を意味していた言葉です。
しかし、時代が進むにつれて、
「チョン」という言葉が特定の民族を指す表現と受け取られることも増えてきました。
その結果、放送禁止用語として扱われるケースが多くなっていったのです。
- 蛭子能収さんはテレビ番組で「バカチョンカメラ」と発言し話題になった
- その意図は冗談や昭和的な表現であり、差別目的ではなかった
- このやり取りが広まり、イメージとして定着した

言葉は時代や価値観によって印象が大きく変わるものだなと、私自身も改めて感じました。
次は、SNSでの反応や今現在の使われ方についてもチェックしていきましょう!
SNSでの反応や”バカチョンカメラ”現在での表現方法
バカチョンカメラという言葉は、
昭和〜平成初期までは一般的に使われていました。
しかし、近年ではSNSやインターネット上で「不適切な言葉」として指摘されることが増えています。
実際にSNS上では、次のような声が見られます。
- 「昔は普通に聞いたけど、今はあまり使わないよね」
- 「差別用語扱いになっているとは知らなかった」
- 「蛭子能収さんが言っていたのを見て初めて意味を知った」
また、テレビや雑誌などのメディアでは現在ほとんど使用されていません。
放送禁止用語リストにも掲載されているケースがあり、公共の場では使わないほうが良い表現とされています。
ただし、あくまで歴史的な言葉として調べる人は今も一定数いるため、今回のように由来や背景を整理する記事も検索されています。
- SNSでは「使わない方がいい」との声が多い
- テレビやメディアでは現在ほとんど使用されていない
- 歴史的な背景を調べる目的で検索されることはある

時代の流れを感じますよね。
意味を知らずに使ってしまうこともあるからこそ、
こうして改めて確認しておくのも大事だなと思いました!
【まとめ】バカチョンカメラの由来や方言との関係・蛭子能収の発言とは?
今回の記事では、バカチョンカメラという言葉の由来や意味、蛭子能収さんの発言との関係についてご紹介していきました。
- バカチョンカメラは「誰でも簡単に使えるカメラ」を意味する言葉だった。
- 「チョン」という言葉は方言や俗語が由来で、もともと差別的な意味はなかった。
- 蛭子能収さんのテレビ番組での発言がきっかけで話題になった。
- SNS上では現在「使わない方がいい」という意見が多く、放送禁止用語として扱われている。
昔は当たり前のように使われていた言葉でも、時代や価値観の変化によって、その受け取られ方が大きく変わることがあります。
特に公共の場では、相手を不快にさせないように気をつける必要がありますね。

でも、こうして由来や背景を知ると、言葉を大切に使うことの大事さに改めて気づきますよね。
また何か気になる言葉があれば、一緒にチェックしていきましょう!
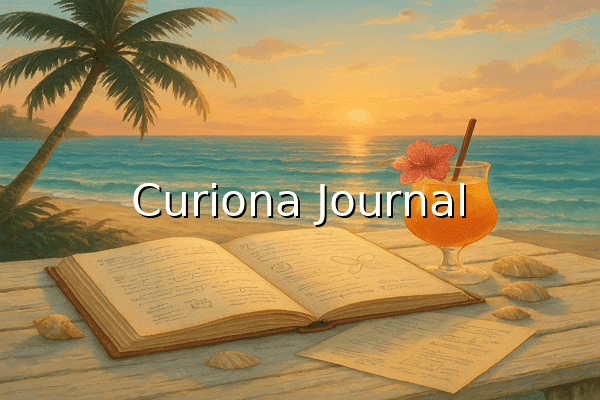









コメント