みなさんこんにちは!
管理人のナリアです。
東京都日野市と立川市をつなぐ日野橋(ひのばし)は、地域の生活道路として長年親しまれてきた多摩川にかかる重要な橋です。
通勤・通学、買い物や散歩にと、毎日のように利用している方も多いのではないでしょうか。
そんな日野橋について、最近こんな声が聞こえてくるようになりました。
- 「新しい橋を作ったばかりなのに、なぜまた壊すの!?」
- 「2回も橋を作るってどういうこと?」
- 「あの橋って“仮”だったの!?」
たしかに、事情を知らなければびっくりしてしまう話ですよね。
でも、実はこの橋の再建計画、もともと決まっていたことなんです。
現在通行している“新しい橋”は「仮橋」と呼ばれるもので、本来の橋を再建するための一時的な措置として作られたもの。
ではなぜ、仮橋を壊してまた元の場所に橋を作り直す必要があるのでしょうか?
そもそも、
最初から本設の橋を作ればよかったのでは?
と思う方も多いはずです。
この記事では、このような素朴な疑問から、
実際の工事計画の背景や意味まで、わかりやすくまとめていきます。
- 日野橋の新しい橋(仮橋)が取り壊す理由
- なぜ2回も橋を作る必要があるのか
- 仮橋と本設橋の違いと意味
- 元の場所に戻して再建する本当の理由
- 「税金の無駄では?」という声や背景

でも調べてみると、ちゃんと理由があって「仮橋は仮橋」だったんですね。
地元の方にも納得してもらえるよう、ひとつずつ丁寧に解説していきますね♪
日野橋はなぜ掛け直される?計画の背景をおさらい
日野橋は、多摩川にかかる重要な生活道路のひとつで、日野市と立川市をつなぐ役割を担ってきました。
ところが、2019年の台風19号により橋脚部分が大きく損傷。
安全な通行ができない状態になり、旧・日野橋の恒久利用は不可能と判断されました。
とはいえ、多摩川を渡るルートが一時的に失われてしまえば、通勤・通学や緊急車両の通行に大きな支障が出てしまいます。
そこで、応急的な措置として旧橋のすぐ横に仮橋(仮設橋)を建設することが決定。
2025年5月14日に仮橋が開通し、現在はその仮橋が使用されています。
そしてこの仮橋の開通をもって、いよいよ本設橋の工事(本物の橋の再建)がスタートするという流れになっています。
計画は最初から“掛け直し”前提だった
実はこの一連の流れは、当初から「仮橋→本設橋」への二段階構成で計画されていました。
仮橋はあくまで一時的な交通確保のために設置されたもの。
恒久利用には耐震性・構造的な課題があり、本設橋を元の場所に再建することが決められていたのです。
そのため、現在使われている仮橋を撤去することも、本来の計画通りなのです。
ポイントまとめ
- 日野橋は台風で損傷し、安全な通行が困難に
- 仮橋は応急的な仮設構造で、2022年に開通
- 最初から「仮橋 → 本設橋」への移行が計画されていた
- 今の橋の撤去は想定内のステップ

でも、こうして調べてみると「ちゃんと段階を踏んだ再建計画だったんだな」ってわかってきました。
引き続き、一緒にその理由を探っていきましょう♪
なぜ日野橋を“2回”作る必要があるのか?
日野橋の「2回建設」に対しては、「税金の無駄では?」という声も上がっています。
でも実は、2回作ることには“ちゃんとした理由”があるんです。
最初に建てられたのは仮橋(仮設橋)。
これは、旧橋が使えなくなった際の緊急措置として設置されたもので、短期間の利用を前提とした簡易的な構造です。
つまり今使っている仮橋は、「仮の通路」。
そのため、恒久的な交通インフラとしては不十分なのです。
仮橋の構造上の限界
仮橋は短期間使用に耐える程度の材料・構造で作られており、耐震性や老朽化への強さが十分ではありません。
また、歩道や自転車道の幅、バリアフリー構造なども本設橋と比べて制限されているため、地域インフラとして“本来あるべき姿”ではないということが言えます。
本設橋への掛け直しは必須だった
こうした理由から、仮橋を使い続けるという選択肢はもともとなく、あくまで仮→本設への移行を前提とした2段階計画が立てられていたのです。
つまり、2回作るように見えても、実際には「段取りどおり」。
橋を再建するための効率的で安全なステップだったというわけですね。
ポイントまとめ
- 現在の仮橋は“仮”であり恒久利用できない構造
- 耐震性・バリアフリーなども未対応
- 仮橋から本設橋への移行は計画通りの流れ
- 2回作るのではなく「段階的な橋の再建」だった

でも、そもそも“仮橋”は本設とは別物。
ちゃんと本物を作る準備段階だったと知ると納得できますね♪
仮橋って本当に必要だった?最初から本設ではダメ?
今回の日野橋の再建計画において、多くの人が感じるのが
「え?仮橋って必要だったの?」
という疑問です。
わざわざ壊す前提で“1本目の橋”を作るくらいなら、最初から恒久的な本設橋を作ればよかったのでは?
そんな声が出るのも、もっともです。
仮橋が必要だった最大の理由は「時間」
実は本設橋(恒久橋)を建てるには、かなりの時間と手間がかかります。
具体的には以下のようなプロセスが必要です:
- 地盤調査・耐震設計・環境影響調査
- 国や都の認可・予算審議・設計契約
- 周辺インフラ・交通動線の整備
こうした工程だけで、数年単位の期間を要するのです。
しかし旧・日野橋は2019年の台風19号で大きく損傷。
通行止めが長引けば、地域の交通が“麻痺状態”になるのは明らかでした。
横に仮橋を架けたのは、再建のための「空け地」確保でもある
元の橋を撤去してから新しく作るには時間がかかる。
でも交通は止められない――
そのジレンマを解決する方法として、
「横に仮橋を作って、そっちで通行してもらおう」という判断が採用されたのです。
実は仮橋の場所は「仮設用地」として短期利用が想定された範囲であり、本設橋の建設が終われば、仮橋を撤去して自然環境や河川管理を元に戻す計画も含まれていました。
仮橋は「ムダ」ではなく「市民の命綱」だった
数年間、交通機能を失わずに地域インフラを維持する。
それが仮橋の最大の目的です。
たとえ一時的なものでも、通学路や救急ルート、物流の動脈として機能してきた仮橋。
その役割を考えると、「最初から本設橋でよかったでしょ?」とは言い切れない現実があるのです。
ポイントまとめ
- 本設橋の建設には調査・認可・設計などで数年かかる
- 仮橋は「緊急対応」として必要不可欠だった
- 横に仮橋を架けたのは、本設スペース確保のためでもある
- 仮橋は“市民生活の命綱”として機能してきた

でも詳しく知ると、それは「つなぎ」じゃなくて“守りの要”だったんですね。
次は、仮橋と本設橋の具体的な違いについて見ていきましょう♪
仮橋と本設橋の違いとは?構造や目的を比較!
仮橋と本設橋──見た目にはそこまで大きな違いがないように思えますが、実はその役割も構造も、根本から異なります。
「仮橋をそのまま使えばいいじゃん」と思う方も多いかもしれませんが、
仮橋はあくまで“つなぎ”の存在。
恒久的な交通インフラとしては使えない理由が、いくつもあるのです。
構造の違い:材料・耐震性・耐久性が別物
仮橋は、簡易構造と短期使用前提で設計されています。
使用される資材も、仮設資材や軽量部材が多く、大規模な地震や長期利用に耐える仕様ではありません。
一方、本設橋は数十年単位での使用を見据えて設計されており、耐震・防災・バリアフリー・歩道幅なども基準をクリアする必要があります。
役割の違い:仮橋は“つなぎ”、本設橋は“未来の基盤”
仮橋の役割は、災害や緊急時に交通を確保するための一時的な橋です。
一方で本設橋は、地域の交通網を支える「正式な道路インフラ」。
自治体・国土交通省の管理下で法的にも恒久インフラとして登録されます。
このように、仮橋は「とりあえず渡れる橋」、本設橋は「安全・長寿命・使いやすさ」すべてを備えた公共財と言えるのです。
ポイントまとめ
- 仮橋は短期前提の仮設構造で、材料や耐震性が本設とは異なる
- 本設橋は数十年使うことを前提に、法的にも正式な公共インフラ
- 仮橋は「応急措置」、本設橋は「都市計画の一部」
- 見た目以上に、安全性や耐久性の差が大きい

でも実際は、構造も役割もぜんぜん違うもの。
本設橋は“未来の安全”を考えた本物のインフラなんですね。
税金の無駄?住民の声やSNSの反応は?
日野橋の再建計画に対して、ネット上ではこんな声も見られます。
- 「新しい橋を作ったばかりなのに、また壊すの?税金の無駄じゃない?」
- 「最初からちゃんとした橋を作ればいいのに…意味わからん」
- 「2回も橋を作るって、ちょっと異常じゃない?」
“仮橋”という言葉のイメージが浸透していなかったことで、「完成したのにまた壊すの?」という誤解を生んでしまった部分もあるようです。
実際には「税金の無駄」とは言い切れない
たしかに、橋を“2回”作ると聞けばインパクトはありますが、実際には計画当初から「仮橋→本設橋」への移行が想定されていたもの。
その意味で言えば、「2回作る」ではなく「段階的に整備する」と表現するのが正確です。
また、仮橋によって地域住民の生活や物流が止まらずに済んだことも、結果として“被害を最小限に抑える”税金の使い方だったとも言えます。
誤解されやすいからこそ、丁寧な説明が大切
仮橋と本設橋の違い、元の位置に戻す必要性、仮橋が一時的な措置であること…
こうした背景を知らないと、どうしても「ムダに見える構造」になってしまいます。
だからこそ、自治体や報道には「説明の丁寧さ」が求められる時代でもあるのかもしれません。
ポイントまとめ
- 「また壊すの?」という誤解の声がSNSで多く見られる
- 仮橋→本設橋は計画通りで、税金の無駄とは言い切れない
- 仮橋があったことで地域の交通は守られていた
- 情報不足が誤解を生みやすく、説明の丁寧さが課題に

確かに“税金の無駄”って思う気持ちもわかります。でも知ってみると、ちょっと見え方が変わってきますよね。
最後に、今回の橋の再建計画をあらためて整理してみましょう♪
【まとめ】日野橋の新しい橋(仮橋)はなぜ取り壊す?2回も作る本当の意味や理由とは?
今回の記事では、日野橋の仮橋がなぜ取り壊されるのか?
そして「2回も橋を作る必要があるの?」という素朴な疑問について、計画の背景と意味を整理してきました。
「えっ、作ったばかりの橋を壊すの!?」と驚く気持ちはとてもよくわかります。
でも実際には、仮橋はあくまで“つなぎ”としての応急措置であり、
本設橋(恒久的な正式な橋)を元の位置に作り直すことが、最初から計画されていたんですね。
2回作るように見えて、実は「段階的にしっかりと地域インフラを守る」ための判断だった、というわけです。
この記事でわかったこと
- 日野橋の仮橋は、2019年の台風による旧橋損傷に対応した応急措置だった
- 本設橋を作るには時間と手続きが必要で、仮橋で交通を維持する必要があった
- 仮橋を撤去し、元の位置に本設橋を作ることは計画通り
- 仮橋と本設橋は構造も目的も異なり、代用できない
- 「2回作る」は誤解で、実際は段階的な再建だった

これを機に、身近なインフラの仕組みや再建の裏側にも、少しだけ目を向けてみると面白いかも♪
最後まで読んでくださってありがとうございました!
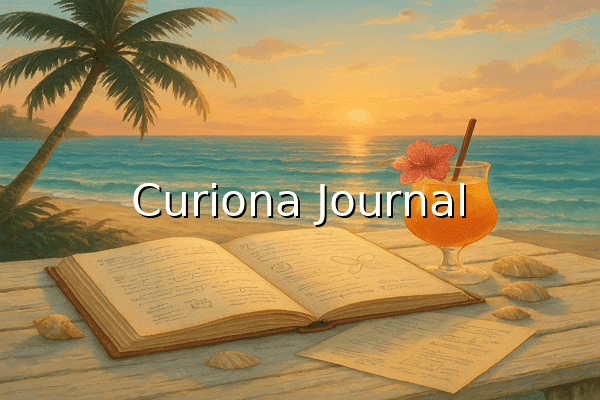









コメント