みなさんこんにちは!
管理人のナリアです。
「ゲンを突きつけるんだ」
そんな言葉を胸に、アメリカで英語版『はだしのゲン』を翻訳・出版した人物がいます。
大嶋 賢洋(おおしま まさひろ)さん。
若き日に平和行進で渡米し、現地で出会った人々の反応から、漫画の力に確信を持ったといいます。
その行動力と信念は、NHKのドキュメンタリー番組『新プロジェクトX』でも紹介され、放送後には年齢や経歴、wikiなどを調べる人が急増しています。
この記事では、大嶋賢洋さんのプロフィールや経歴、はだしのゲンとの関わりをわかりやすく解説し、翻訳に込めた想いやエピソードもご紹介します。
- 大嶋賢洋さんの年齢・プロフィール・名前の読み方
- アメリカ横断と経歴、はだしのゲン翻訳に込めた思い
- 新プロジェクトXで紹介されたエピソードや現在の活動状況

「ゲンを突きつけるんだ」
その言葉がすべてを物語っている気がしますね。
自費で翻訳を始めたなんて、本当にすごい…。
番組を見て気になった方も、この記事で大嶋さんの思いや背景をぜひ知ってほしいです!
大嶋賢洋(おおしままさひろ)とは何者?
大嶋賢洋さんは、漫画『はだしのゲン』の英語翻訳を手がけた人物として注目されています。
英語版として最初に出版されたのが1978年で、その中心的な存在となったのが大嶋さんでした。
1976年、当時26歳だった彼は平和行進のためにアメリカを徒歩で横断。
現地で原爆について語りかけるも、「それは神の罰だ」と言い放つ声にぶつかります。
原爆の真実が伝わらないという壁を痛感した瞬間でした。
そのとき思い出したのが『はだしのゲン』。
日本から取り寄せて見せると、言葉が分からないアメリカ人が涙を流してページをめくったといいます。
「漫画なら伝わる」と確信した彼は、仲間たちとともに英訳に取り組み、1978年に数百冊の第1巻を印刷・配布しました。
- 大嶋賢洋は、英語版『はだしのゲン』制作の中心的存在
- アメリカ横断中に「伝わらない壁」とぶつかる経験をした
- 翻訳チームと共に英語版を印刷・配布し、海外へゲンを届けた

“はだしのゲンなら伝わる”って確信した瞬間、すごく感動的ですよね。
言葉の壁を越えて、絵と物語で伝えるって…まさに「突きつける」行動だったと思います。
この行動力と信念が、多くの人の心を動かしたのも納得です。
大嶋賢洋の年齢やwiki風プロフィール
年齢は?【2025年時点】
大嶋賢洋さんの年齢は73歳です。
(2025年現在)
プロフィール(出身・学歴・経歴)
| 名前 | 大嶋賢洋(おおしま まさひろ) |
|---|---|
| 生年/年齢 | 1949年(73歳) |
| 出身地 | 北海道帯広市 (帯広小・帯広第一中・帯広三条高校卒) |
| 最終学歴 | 東洋大学第二文学部仏教学科 中退 |
| 職業経歴 | 編集者 筆者 小説同人誌立ち上げ 図解書シリーズ著者など |
このたび小説家デビューとなった大嶋賢洋さんは、先日7/26「#新プロジェクトX」に出演! 『#はだしのゲン』初の英語翻訳プロジェクトに携わっていました。どんな人物か気になった方はぜひ、現在NHKプラスで視聴できますのでご覧ください☆https://t.co/m75WyME3Zi
— 太田出版なかのひと (@OHTABOOKS_PR) July 28, 2025
学生時代は仏教学を専攻しながら、編集者としてキャリアをスタート。
その後、2007年に集英社から『定年バックパッカー読本』でデビューし、図解14歳シリーズなどの企画制作でも知られるようになりました。
50歳で小説同人誌「DRUG」を仲間と創刊し、小説執筆へ。
故郷帯広を舞台にした物語でデビュー作を発表しています。母親への介護経験や帯広への想いが反映された作品は地域でも話題になりました。
- 大嶋賢洋さんは1949年北海道帯広市生まれ、年齢は73歳。
- 帯広三条高校卒、東洋大第二文学部仏教学科在学(中退)
- 編集者、小説家、図解シリーズ著者として活動

帯広出身で編集から表現まで幅広く活動してきた経歴、実に魅力的です!
デビューが50歳というのも、続ける覚悟と熱意の現れですね。
誰もが真似できる経験じゃない…本当に尊敬です。
大嶋賢洋の経歴|翻訳者になるまでの歩み
旅好きヒッピー時代と平和行進
大学在学中、大嶋賢洋さんは編集の仕事に携わりつつも、“旅好きのヒッピー”として世界を歩くことを選びました。
1976年、26歳のときには米国の反核団体による「平和行進」に参加し、アメリカ大陸を約10カ月かけて徒歩で横断しています。
その最中、「原爆は神の罰だ」と言い放つアメリカ人に出会い、大嶋さんは深く傷つきます。
原爆の悲惨さを伝えようとしても、写真や資料では通じない──
そんなとき、思い出したのが日本で読んだ『はだしのゲン』でした。
「ゲン」との出会いと翻訳への決意
すでに刊行されていた1巻〜4巻を日本から取り寄せ、現地で出会った人々に読ませたところ、言葉が分からないにもかかわらず涙を流して読み続けた人もいたそうです。
この体験から、「漫画なら伝わる」「英語に翻訳すればもっと届く」と確信。
帰国後すぐに作者・中沢啓治さんの元を訪ね、翻訳の許可を願い出たところ、
「読んでもらうんじゃない。ゲンを突きつけるんだ」
と力強く背中を押されたといいます。
- 26歳で平和行進に参加し、アメリカを徒歩で横断
- 原爆の真実が伝わらない壁を体感する
- 『はだしのゲン』を手に、翻訳という使命を見出した

アメリカ横断の途中で「ゲン」と出会ったエピソード、本当に映画みたいです。
そのまま翻訳に動いて、中沢さんにも会いに行く行動力…すごすぎます。
「突きつけるんだ」って言葉、強く心に残りますね…。
『はだしのゲン』英語版翻訳の背景と苦労
翻訳作業の難しさと、仲間との夜なべ作業
翻訳の許可を得た大嶋賢洋さんは、仲間たちとチームを組んで翻訳作業に着手。しかし、そこには大きな壁が立ちはだかりました。
とくに苦労したのは、吹き出しの英訳置き換え。
当時はPCもなく、1コマの処理に2時間以上かかることも珍しくありませんでした。
“夜な夜な集まって翻訳する”という地道な作業の積み重ねだったそうです。
協力者たちと広がったボランティアネットワーク
英訳を進める中で、アメリカ人の留学生・アラン・グリースンさんや、日本人翻訳者の西多喜代子さんらと出会い、翻訳ボランティアのネットワークが全国に広がっていきます。
米国ではその後、現地出版社が出版を引き受け、第4巻までが刊行。
最終的に全10巻の英訳が完了したのは2009年のことでした。
ページ構成も逆!“反転処理”の苦労とは
日本と海外では、本のとじ方・コマ割りの方向が真逆。
そのため大嶋さんたちは、すべての絵を左右反転して英語を入れ直すという、想像を絶する作業を行っていたのです。
当時の資料によれば、原稿を1ページ1ページ手作業で修正・校正し、英語の吹き出しに合うように絵を調整していたとのこと。
単なる翻訳ではなく、“再構成”に近い仕事でした。
- 翻訳はすべて手作業!1コマに2時間かけることも
- 全国の有志が集まった翻訳ボランティアの輪
- 反転処理や英語配置など、地道な努力が全10巻出版に繋がった

想像以上に、手作業での作業が大変すぎて驚きました…!
ページの向きや吹き出しの配置って、当たり前じゃないんですね。
それでも最後までやり遂げたって、本当にすごいです…!
大嶋賢洋に関するよくある疑問(Q&A)
現在は何をしているの?
現在の明確な活動拠点や職業については公開情報が少ないものの、最近も『はだしのゲン』の英語版翻訳者として、イベントや講演に登壇する機会があるようです。
2024年には、広島で行われた連載50周年イベントにオンライン参加。
元翻訳チームのメンバーとも再会を果たしています。
wiki(Wikipedia)はあるの?
2025年7月時点では、Wikipediaに「大嶋賢洋」個人のページは存在していません。
そのため、多くの人が「wiki」「プロフィール」などで検索して情報を探しているようです。
本記事は、Wikipediaに準じた構成で情報をまとめた内容となっていますので、参考にしていただければと思います。
SNSやメディア出演歴は?
公式なSNSアカウント(Twitter/Facebookなど)は確認されておらず、個人として発信している様子は見受けられません。
ただし、NHK『新プロジェクトX』への出演や、翻訳関係者としての取材記事(毎日新聞、ヒロシマ平和メディアセンターなど)でたびたび紹介されています。
- 現在の活動は限定的に把握できるが、講演等には参加している
- Wikipediaの個人ページは存在しない
- 公式SNSはなく、TV番組や新聞記事で紹介されることが多い

Wikipediaがないのはちょっと意外でした!
でも、こうして情報がまとめられてると安心ですね。
SNSをしていないのも、むしろ信念を持って静かに活動してる感じがしてかっこいい…!
まとめ|大嶋賢洋が世界に伝えた“ゲンの心”
- 大嶋賢洋さんは『はだしのゲン』英語版翻訳の中心人物
- アメリカ横断中の経験から翻訳の必要性を痛感
- 仲間たちと翻訳チームを結成し、10年以上の歳月をかけ全10巻を完成
- 現在も平和活動や講演を通してメッセージを発信
『はだしのゲン』の翻訳を通じて、日本の被爆体験と反戦の思いを世界に届けた大嶋賢洋さん。
“読む”のではなく“突きつける”という言葉に象徴されるように、その行動力と信念は今も多くの人々に響き続けています。
今後も、静かに力強く、戦争を語り継ぐ活動を続けていくことでしょう。
誰かの「知らなかった」を「知ってよかった」に変える。
そんな存在であり続けてほしい人物です。

「ゲンを突きつける」って、やっぱり心に残る言葉ですね。
ただ翻訳するんじゃなくて、“伝える”という覚悟がすごく伝わってきました。
今の時代だからこそ、もっと多くの人に知ってもらいたい方です!
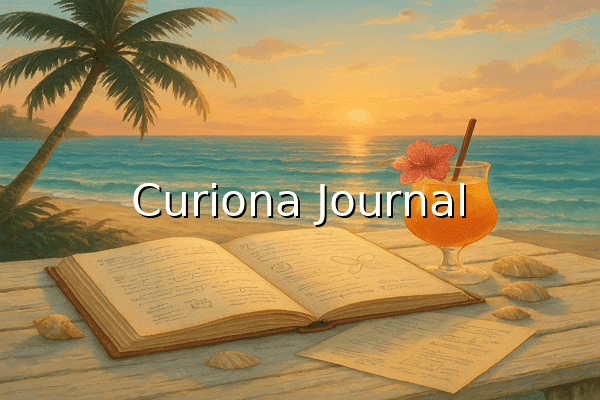



コメント